
お悩み相談コーナー①
Q. 子ども服って可愛いけれど、そんな服に限って子どもがなかなか着てくれないんだよね…。
A. もしかしたら「自分で着づらい」ことが原因かもしれません。一人で着脱できれば「できた!」自信がつき、「次も自分で着たい」というやる気につながりますよ。
自分で着替えればやる気が育つ!
幼児が着脱しやすい子ども服の選び方
子どものやる気が育つ、着脱しやすい服の選び方を紹介します。
「自分でやりたい!」という気持ちになれる服を選ぼう
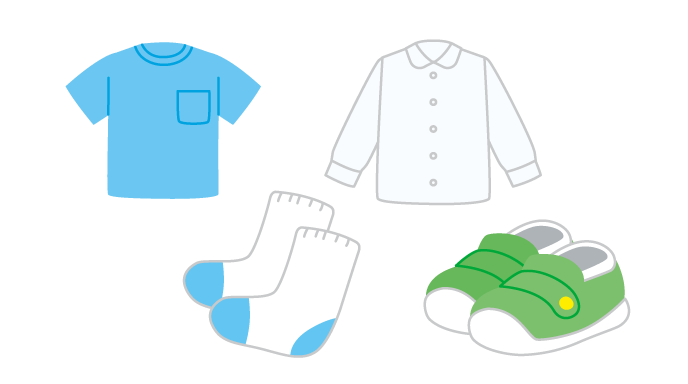
子ども服って可愛いですよね。大人顔負けのデザインもあり、保護者のかたも選ぶのが楽しいのではないでしょうか。でもそんな服に限って、子どもが着てくれないということはありませんか?それはもしかすると、「自分で着づらい」ことが原因かもしれません。特に、保育園や幼稚園に着ていく服は、デザインよりも着脱のしやすさが重要です。ボタンが多かったり、ピタッとしていたりする服だと大変。「一人で着脱できる服」ということを心がけて選んでみるといいでしょう。
着脱しやすい子ども服の選び方
・伸縮性がある服を選ぼう
上下とも、なるべく伸び縮みするゆったりとした服を選びましょう。特に小さいお子さまの場合、握力や腕力もまだ弱いので、ピッタリしている服は大変です。大人も、スキニータイプのジーパンより、ジャージのほうが着脱しやすいですよね。保護者のかたが楽だと思う服が、子どもにとっても着やすい服です。
子どもはまず「脱ぐ」ことから着脱を覚えていきます。これは、着るよりも脱ぐほうが簡単だからです。興味を持ち始めた子どもが「やりたい」と思えるような服にしてあげれば、どんどん着脱が上手になっていくでしょう。
・前後がわかりやすい服を選ぼう
子どもにとって、服の前後という微妙な違いはわかりにくいものです。ですから、誰が見てもはっきり前後がわかる服を選ぶとよいでしょう。
特におすすめなのは、前だけにイラストやワンポイントが付いているもの。リボンや飾りボタン、ポケットが付いているものでもいいでしょう。
反対に、無地の服や、前後同じ柄の服はわかりづらいです。この場合は、小さなアップリケなどで目印を付けてあげるといいでしょう。
・重ね着はしすぎないようにしよう
寒い季節はつい重ね着をさせたくなりますよね。でも、重ねすぎはおすすめしません。先に着た服を巻き込んだりして、うまく着脱できないからです。
寒い日は、3枚+ジャンパーという組み合わせがおすすめです。具体的には、「下着」「厚手の服(トレーナーなど)」「袖がないベストやチョッキ」という感じ。袖がないベストは着脱しやすいですし、暑ければ脱ぐことができるので便利です。外に行くときは、ここにジャンパーやコートを羽織れば温かくなります。
・ボタンは大きなものを選ぼう
3歳くらいになると、ボタンにも興味を持ち始めるでしょう。上手にボタンかけができるように、普段着る服にも取り入れてあげると◎です。
はじめは、大きめのボタンのものを選びましょう。ボタンの数は少なめがおすすめです。まだ指先が器用でないお子さまでも、無理なく練習することができるでしょう。上手になってきたら、少しずつ小さいボタンにしていってもOKです。
ただし、保育園や幼稚園の中には「ボタンの服はNG」というところもあるので、きちんと確認をしてください。もしNGであれば、お休みの日などにボタン付きの服を着るようにしましょう。
着脱しやすい服は、動きやすさも兼ね備えています。思い切り体を動かせるので、保育園や幼稚園に行くとき、外遊びのときにもぴったりです。
もちろん、デザインだって子どものやる気を引き出すのに必要なことがあります。着脱のしやすさだけでなく、気持ちの面で「やりたい」と思えることも大切です。お子さまと一緒に服を買いに行くのもいいかもしれませんね。

情報元:ベネッセ 教育情報サイト
自分で着替えればやる気が育つ!幼児が着脱しやすい子ども服の選び方|ベネッセ教育情報サイト (benesse.jp)

お悩み相談コーナー②
Q. 朝の忙しい時間、子どもに早く着替えてほしいのに、ぐずったりゴロゴロしていたりで全然身支度が進みません。どうしたらいいですか?
A. 着替えたがらない理由には、着替え以外の理由がある場合も。理由にあわせて対処法を考えましょう。やる気につながりますよ。
子どもが着替えを嫌がる……服を着せるのに時間がかかる時の理由と対処法
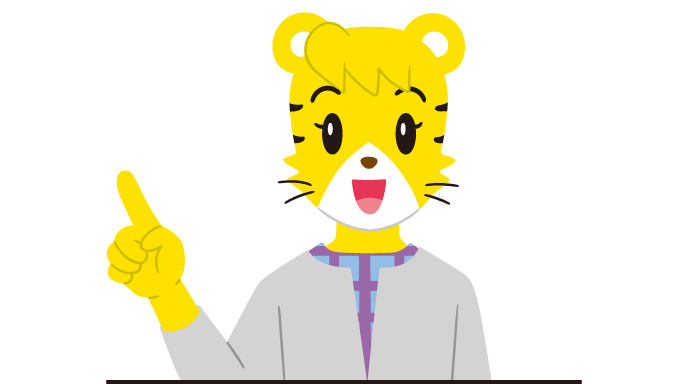
「着替えない」と一口に言っても、その理由は子どもによって異なります。ただ、大きく2つに分けることは可能です。
①「着替えそのものに理由がある」
②「着替え以外に理由がある」
まずは、このどちらなのかをきちんと見極めることが大事。着替えのことなので「着替えそのもの」に着目しがちですが、それだと②の場合はうまくいきません。お子さまをよく観察したり、話をじっくり聞いてあげたりすることで、着替えない理由を探ってみましょう。そうすれば対処法もわかってきます。
①「着替えそのものがイヤ」な場合の子どもの気持ちと対処法
まずは「着替えそのものに理由がある」場合です。こちらは、年齢が低かったり、イヤイヤ期真っ最中だったり、こだわりが強かったりするお子さまに多く当てはまります。
・「服が着づらい!」「わかりづらい!」
服そのものが着づらいと、着替えがイヤになることがあります。「サイズが小さい」「伸縮性がない」「ボタンが多い」などですね。「前後がわかりづらい」という服も、子どもにとってストレスになることがあります。感覚が過敏なお子さまの場合は、素材も注意してあげたいですね。
上手に着られるように練習していくのは大事なこと。ただ、余裕がなくてお互いイライラしてしまったらやる気がなくなってしまいます。平日の朝は、一人でも着られるゆったりした服を選んであげて。お休みの日や夜など、着替えをじっくり見てあげられるときに練習をするとよいかもしれません。
・「自分の着たい服じゃない!」
自我が芽生えてくると、服も自分で選びたくなります。そうすると、保護者のかたの選んだ服を嫌がることも。同じ服ばかり着たいというこだわりがある場合も同様です。
この場合は、お子さまに選ばせてあげるのが一番。前日に決めておくとスムーズです。「どっちにする?」と2つから選ばせてあげる方法もアリ。変な組み合わせになってしまうこともありますが、お子さまが決めたのであれば尊重してあげましょう。その方がスムーズに登園できる可能性が高くなります。
・「『今は』着替えたい気分じゃない!」
日によって着替えたり着替えなかったりする場合は、こういった理由も考えられます。遊びを中断されたり、まだ目が覚めていなかったり……。この場合は、子どもがやりたいことが一段落するまで待ってあげるのがベスト。ただ、忙しい朝はそんな時間もありませんよね。そんなときは「長い針が6になったら着替えよう」など、予告をしておくとうまくいく可能性が高いです。
また、保護者のかたが着替えてほしいタイミングと、子どもが着替えたいタイミングは違うことがあります。食事の前なのか後なのか、起きた直後なのか出かける直前なのか……。大人の都合で時間を決めずに、お子さまに着替えたい時間を聞いてみるとスムーズに進むかもしれません。
・「自分でやりたいのにうまくいかない!」
イヤイヤ期の子どもで多いのが、「全部自分でやりたいけどうまくいかない」というもの。着替えも同じです。そしてこの時期は、良かれと思って手を出すことがマイナスになってしまうことがあります。
一番の理想は、時間に余裕を持って子どもがやっているのをじっと待つこと。つい口や手を出したくなりますが、なるべくお子さまの「やりたい!」を優先してあげましょう。忙しいときは、「ここだけ手伝っていい?」「仕事に遅れちゃうから今日だけやらせて」と一言かけると納得できる可能性が高くなります。I(アイ)メッセージを意識して、声をかけてあげましょう。
・「着替えが嫌い!」「なんだか苦手!」
感覚的なものや、気分的なもの、さまざまな理由で着替えという行為自体が苦手な子どももいます。この場合は、安心感を与えてあげることが必要。着替える場所を配慮したり、不快感の少ない服を選んだりして、お子さまの不安要素を取り除いてあげましょう。着替えの必要性(清潔さや動きやすさなど)も、時間をかけて教えていってあげてください。
また、保護者のかたに「そうじゃない」「遅い!」と注意されることがイヤで着替えが苦手になる子どももいます。始めは間違って当然。この時期はとにかく、一人で着替えられたことを認めてあげましょう。そのうえで、「ここを直すともっとカッコいいよ、やってみる?」と声をかけてあげてください。嫌がればそのままでOK。保育園・幼稚園に裏返しの服を着ていっても、先生たちは快く迎えてくれるはずです。
②「着替え以外に理由がある」場合の子どもの気持ちと対処法
ほめても励ましても服を変えてもうまくいかない……。そんなときは、「着替え以外に理由がある」に当てはまる可能性が高いです。ちょっと視野を広げて、着替えをしない理由を考えてみましょう。
・「もっと遊んで!」「もっとかまって!」
ぐずったり泣いたりするだけでなく、笑って逃げ回ったり、わざと服を脱いでみたり……。そういった行動が見られるときは、保護者のかたにかまってもらおうとしている可能性があります。必然的に触れ合うことができる着替えの時間。泣いたり怒られたりしても、保護者のかたとの関わりを増やそうとしているのかもしれません。
余裕がなくてスキンシップが減っていたり、話をする時間が少なかったり……。入園すると、どうしても子どもとの時間は減ってしまいます。「最近関わりが減っているかも」と思ったら、ちょっと意識して生活全体でスキンシップを増やしてみましょう。そうすることで「着替え以外でもパパ・ママと触れ合える」と思えるようになるはず。結果的に、朝の着替えも少しずつスムーズになるかもしれません。

・「保育園・幼稚園に行きたくない!」
園に行きたくないから着替えない、という可能性もあります。その場合は、そちらの原因を取り除いてあげる必要があるでしょう。「給食がイヤ」「行事の練習が大変」など、理由はさまざまです。何か気になることがあれば、先生に相談したり、お子さまの気持ちを聞いたりしてみてください。着替えの時間ではなく、余裕があるときに聞いてあげるのがおすすめです。
・「体調が悪い」「眠い」
体調がすぐれないと、思うように体が動きません。特に小さい子どもの場合は、言葉の代わりにぐずったり泣いたりすることで体調不良を表現することも多いです。「何かおかしい」と思ったら、体調不良を疑ってみてください。
また、眠いというのも体調不良と同じ。生活リズムを改善したり、着替える時間を後ろにずらしたりして、目が覚めている状態で着替えられるようにするとよいかもしれません。
・「甘えたい」
本当は自分でできるのに「やって」とぐずる場合は、甘えたいのかもしれません。かまってほしい気持ちと似ていますね。きょうだいが生まれる前後や、入園直後などに多く見られます。
この時期は、全部やってあげてもOK。忙しい平日の朝は、お子さまの「甘えたい」という気持ちを優先してあげてよいでしょう。着替えを練習するのは、夜や休日にゆっくりと。もちろん、着替え以外の場面でたくさんスキンシップを取ることも大切です。
【全部やってあげても、うまくできなくてもOK!完璧を目指さないで】
着替えない理由はさまざま。ただ、どんな状況であっても忙しい平日の朝に子どもの着替えと向き合うのは大変です。どうしても着替えないことはありますし、イライラすることだってあります。
ですから、着替えに対するハードルを少し下げてみてください。甘えたいときは全部やってあげてもOK。裏返しに着てしまっても自分で着られたならOK。変な組み合わせでも本人が満足していればOK。園に送っていったときに「今日は自分で着ました!」と伝えれば、先生も笑顔で迎えてくれるでしょう。
着替えの練習は、夜や休みの日にもできます。そこで自信をつけたり経験を積んだりすれば、いずれ朝の着替えもスムーズになってくるはず。毎回完璧を目指さなくても大丈夫です。

情報元:ベネッセ 教育情報サイト
子どもが着替えを嫌がる……服を着せるのに時間がかかる時の理由と対処法|ベネッセ教育情報サイト (benesse.jp)

お悩み相談コーナー③
Q. マイペースな子で朝の身支度に時間がかかりすぎます。もっとてきぱきできるようにするには?
A. 工夫することと手伝うことが大切だと思います。いろいろ工夫してみましょう。
身支度をてきぱきできるようにする工夫
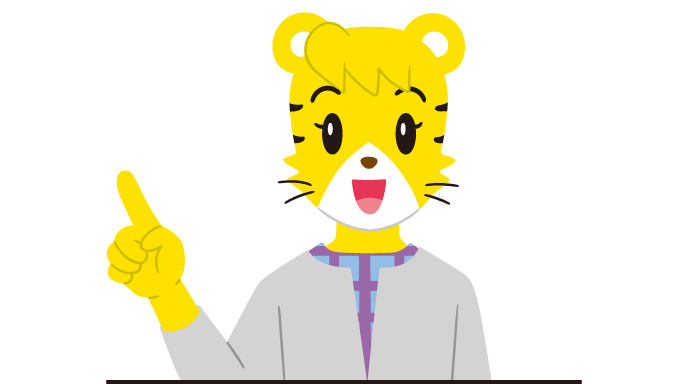
・夜寝る時刻を早めて、朝起きる時刻を早めます。
それによって、親も子も朝の生活にもう少し余裕を持つことができます。
・アナログ時計の横に紙に描いた模擬時計を貼って時間の見える化をします。
模擬時計の針は、朝食を食べ終わる時刻と着替え終わる時刻を指すように描きます。模擬時計に目ざすべき時刻が描かれているので、本物の時計の針が進んで残り時間が減っていくのが目に見えてわかります。これで子どももペースを調整するようになります。
・身支度にかかる時刻をストップウオッチで計って記録します。
新記録が出たら花丸をつけます。あるいは、目標タイムを決めておいてクリアしたらシールを貼るのも良いでしょう。
・レベル方式でチャレンジさせます。
ホワイトボードに下のようなレベルを書いておき、現状のところにキャラクターのマグネットなどを貼ります。
<年少レベル>ママに着替えさせてもらう
<年中レベル>3分で1人で着替える
<年長レベル>2分で!
<1年生レベル>1分で!
<2年生レベル>30秒で!
ただ、ここで気をつけてほしいのがレベルの設定を難しくしすぎないことです。現状で3分かかるならそれを今の年齢にしてください。その子の現状に応じてやる気が出るようにすることが大切です。子どもは「レベル」とか「クリア」などの言葉が好きなので、はりきります。クリアしたら大いにほめてあげてください。下がってしまった場合は、叱るのではなく一緒に悔しがってください。
・やる気の出る言葉がけを工夫します。
たとえば、「早回しでスタート」「2倍速で着替えよう」というだけで楽しみながらスピードアップできます。ときには、反対に「遅回し!」と言ってゆっくりモードでさせてみるのも楽しいです。ストップウオッチを片手に「昨日のあなたと競争だよ。用意、ドン」と言って始めさせるのも良いですね。
・口で言うのではなくカードで伝えるのも良い方法です。
あるお母さんは、「急ごう」「早送り」「あと1分」「たたもう」などと書いたカードを見せるようにしているそうです。口で言うとどうしてもイライラするけれど、カードならそういうこともないそうです。
・音楽を使う手もあります。
「この音楽が流れたら○○を始める」とか「この音楽が終わるまでに○○を終わらせる」などと決めて実践している家庭はけっこうあります。タイマーでセットしておいても良いですね。
 これらの例を参考に、ぜひ皆さんもいろいろ工夫してみてください。ちょっとした工夫でかなりよくなることもあります。やってみてうまくいかないときは、改善したりほかの工夫に切り替えたりしてください。
これらの例を参考に、ぜひ皆さんもいろいろ工夫してみてください。ちょっとした工夫でかなりよくなることもあります。やってみてうまくいかないときは、改善したりほかの工夫に切り替えたりしてください。
それでもうまくいかないときもあると思います。または、「そもそも工夫と言ってもなかなか……」という場合もあることでしょう。そういうときは、手伝ってあげれば良いのです。「親が見ていればできるけれど、見ていないと遊んでしまう」という場合は、終わるまでずっと見ていてあげてください。
でも、「そんな時間はない」とか「見ていても時間がかかる」という場合は、どんどん手伝ってさっさと着替えさせてしまえばそれでオーケーです。これが現実的でおススメな方法です。実際こういう方法で乗り越えてきた親子は星の数ほどたくさんありますし、今現在もたくさんいます。
でも、そのとき2つのやり方があります。
叱りながらやるか楽しみながらやるかです。
そのとき、「自分でやらなきゃダメでしょ」「まったくあんたは……」「なんで自分でできないの」「いつになったらできるの」などという否定的な言い方で叱りながらやるのはやめましょう。こういう言葉は無意味であるだけでなく弊害ばかりです。こういう言葉によってできるようになることはありませんし、言われるほうも言うほうも朝から嫌な気持ちになるだけです。それを引きずったまま家を出るのはよくありません。気持ちが不安定なとき子どもは(おとなでもそうですが)注意が散漫になりますので、交通安全の面でも問題があります。気持ちがクサクサしていると授業にも集中できませんし、友達とトラブルを起こす可能性も高まります。また、否定的な言葉を浴び続けることで、子どもは自分に自信が持てなくなります。「親にあまり好かれていないのかも……」という不安も感じるようになります。
そうではなく、どうせなら楽しくやってください。あるお母さんは口から出任せの歌を歌いながら楽しくやっていたそうですよ。
今から今からお出かけだー♪お出かけ一体どこ行くのー♪そーれは楽しい幼稚園♪ママも行きたい幼稚園♪
そして、ちょっと自分でがんばれた日は大いにほめてあげてください。
 さて、ここまで読んで、「それでは依頼心が強くなって自分でできなくなるのでは? 自立心が育たないのでは?」と感じる人も多いと思います。でも、そんな心配は杞憂です。
さて、ここまで読んで、「それでは依頼心が強くなって自分でできなくなるのでは? 自立心が育たないのでは?」と感じる人も多いと思います。でも、そんな心配は杞憂です。
なぜなら、こういう現実的な方法でしのいでいるうちにだんだんできるようになった子は星の数ほどたくさんいるからです。子どもの成長とはそういうものなのです。
手伝ってもらってできるようになり、できるようになれば依頼はしなくなる、当たり前のことです。
そもそも、今の状態でも件のことができないからと言って、その子は依頼心が強いとか自立心がないなどということにはなりません。ただ、物事をてきぱき処理したり素速く行動したりすることが苦手なだけです。この2つはまったく別問題です。
その証拠に、今だって自分が好きなことややりたいことは親に頼ることなくどんどんやっているはずです。
てきぱきしていない子はたくさんいます。
私の経験ですと、てきぱきしていない子は反面おっとりした癒し系で、友達に優しくてみんなに好かれていることが多いようです。あるいは、事務的な処理能力が遅い分、ユニークな創造性を持っていたりもします。ですから、苦手な部分には目をつむって、その子の良いところをたくさんほめて伸ばして自信を持たせてあげてください。そうしていれば、依頼心が強くなって自立できないということはありません。
親にできることは、方法を工夫したり、言葉のかけ方を工夫したり、楽しく手伝ったり、ほめたりすることです。このようにしながら気長に待っていれば、そのうちできるようになります。

アドバイス:親野智可等(おやのちから)先生(教育評論家)
情報元:ベネッセ 教育情報サイト
マイペースで朝の身支度に時間がかかります[教えて!親野先生]|ベネッセ教育情報サイト (benesse.jp)

「こどもちゃれんじ」「しまじろう」は㈱ベネッセコーポレーションの登録商標です。